購買力平価説
2通貨の交換比率である為替相場には割高・割安を判断する一般的な基準がありませんが、長期では購買力を一つの基準とすることができます。ここでは、為替相場に関する有力な理論である購買力平価説(Purchasing Power Parity Theory)の要点を解説します。
購買力平価説の基本的な考え方
![]() 購買力平価説の原理となっているのは、「A国とB国の間で物やお金の流れが完全に自由なら、同じ商品は同じ価格となるように為替レートは調整されるはずだ」という考え方です。例えば、マクドナルドは世界各国に出店し、均質な商品を供給しています。この考え方に従えば、ビッグマックの値段が米国で3.8ドル、日本で380円とすれば、為替レートは1ドル=100円が適性レートということになります。実際にイギリスの有名な経済誌エコノミストは、ビッグマック指数というものを公表しています(公式サイト→The Big Mac Index)。ちなみに2018年1月のビッグマック指数(基準通貨:ドル)は、米国の5.28ドルに対して日本は3.43ドルでした。購買力平価説に基づけば、日本のビッグマックは割安です。つまりそれだけドルが円に対して強いことを示しています。ちなみに最も割高だったのはスイスフランでした。
購買力平価説の原理となっているのは、「A国とB国の間で物やお金の流れが完全に自由なら、同じ商品は同じ価格となるように為替レートは調整されるはずだ」という考え方です。例えば、マクドナルドは世界各国に出店し、均質な商品を供給しています。この考え方に従えば、ビッグマックの値段が米国で3.8ドル、日本で380円とすれば、為替レートは1ドル=100円が適性レートということになります。実際にイギリスの有名な経済誌エコノミストは、ビッグマック指数というものを公表しています(公式サイト→The Big Mac Index)。ちなみに2018年1月のビッグマック指数(基準通貨:ドル)は、米国の5.28ドルに対して日本は3.43ドルでした。購買力平価説に基づけば、日本のビッグマックは割安です。つまりそれだけドルが円に対して強いことを示しています。ちなみに最も割高だったのはスイスフランでした。
購買力平価説に基づく為替相場
ビッグマックという身近な商品の価格をベースに為替レートを比較することは分かりやすいのですが、購買力は物価全体から総合的に判断されねばなりません。このため、購買力をベースに為替レートを分析するときは、CPI(消費者物価指数)やPPI(生産者物価指数)など、いくつかの物価指数を使うことが一般的です。
下図は財団法人国際通貨研究所が公表しているドル円の購買力平価のチャートです(2018年2月時点)。赤が消費者物価指数を、緑が企業物価指数を、水色が輸出物価指数を基準とした購買力平価です。赤と緑が1973年を、水色が1990年を基準として指数化されており、これを相対的購買力平価と言います。そして紺が実際の為替相場(月中平均)を示しています。長期的に見ると、為替相場は企業物価指数をベースとした購買力平価に回帰していることが分かります。
なお、相対的購買力平価を式にすると「起点時点における実勢為替相場×(自国の物価指数/外国の物価指数)」で表わされます。
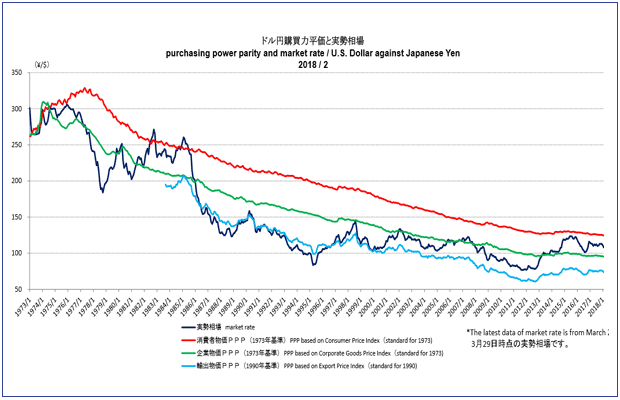
| 実際の為替相場(月中平均) | 消費者物価ベース | 企業物価ベース | 輸出物価ベース |
| 107.90 | 124.41 | 95.19 | 73.64 |
内閣府が公表した購買力平価
もう一つ例を挙げておきます。下図は内閣府のサイトに掲載されていた、購買力平価説に基づく為替相場のチャートです。縦軸にドル/円のレート、横軸に西暦をとっています。データが古く画像も粗いので恐縮ですが、ご参考までに転載しました。このチャートでは、購買力を算出するために消費者物価、国内卸売物価(≒生産者物価)、製造業GDPデフレータ、輸出物価の各種物価指数を比較使用しています。これらをベースにして理論的な為替レートを求めているのです。大雑把に言うと、長期的なドル/円のレートは、消費者物価ベースと輸出物価ベースで計算されたレートの間で推移していることが分かります。
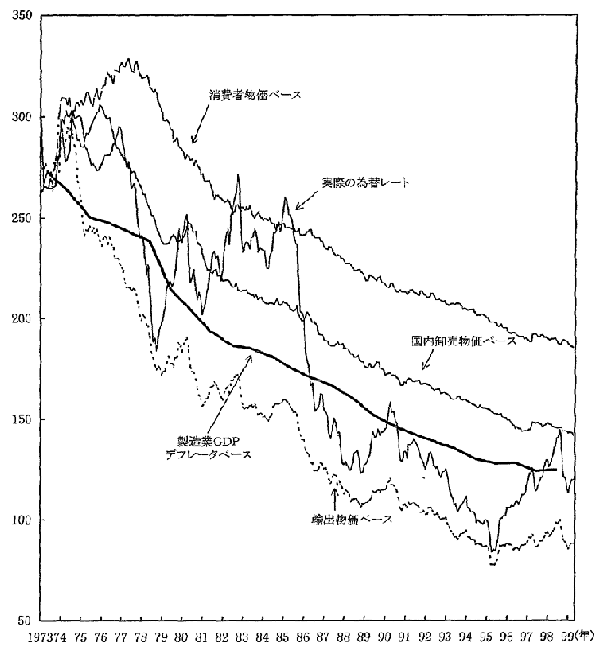
- 参考記事:ドル/円相場の月足チャート(対数チャート)
購買力平価とインフレ
購買力平価説の考え方に基づくと、インフレ率も為替相場に影響を及ぼす重要な要因となります。例えば先ほどの例で、ビッグマックの価格が、米国ではインフレのために5ドルに上昇する一方、日本では変わらないとします。すると、5ドル=320円から導かれる為替レートは64円です。インフレは通貨価値の下落ですから、日本よりもインフレ率の高い米国のドルは、対円で下落することになるわけです。実際の相場では、インフレ率の高い国は金利も高いので、資金が集まって上昇する場合もあります。しかし、金利からインフレ率を差し引いた実質金利が高いか安いかが問題です。名目金利が高くても、実質金利が低ければ、その通貨は長期的には下落する可能性が高いと言えます。
- 参考記事:為替相場とインフレ(デフレ)